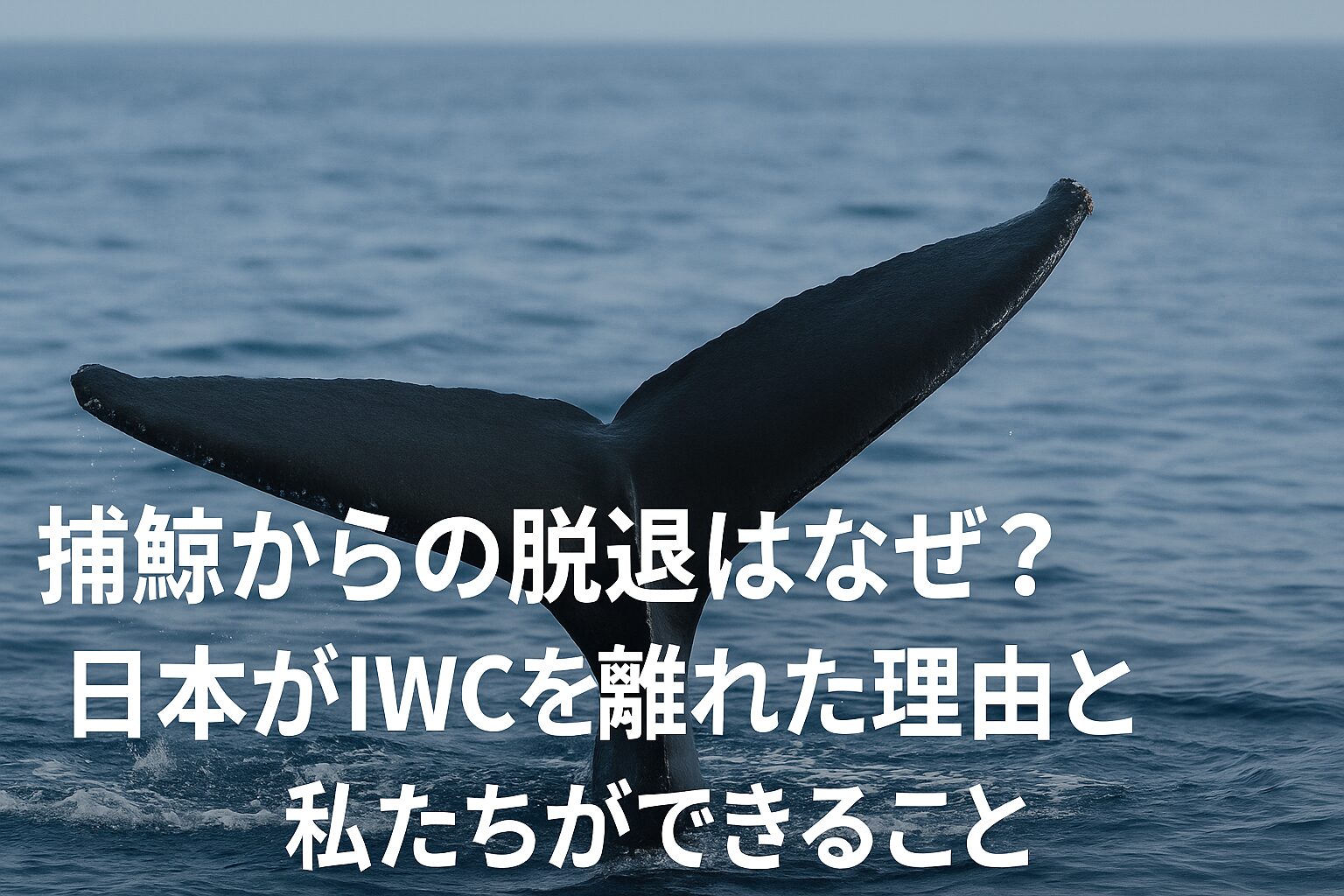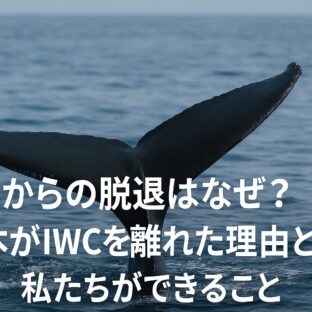日本の捕鯨とIWC脱退:その理由と私たちにできること
はじめに
2019年6月30日、日本は国際捕鯨委員会(IWC)から正式に脱退しました。この決定は国内外で大きな波紋を呼び、賛否両論が巻き起こりました。なぜ日本はIWCを脱退したのか、そしてこの問題について私たち一人ひとりができることは何なのか。本記事では、日本の捕鯨問題を多角的に掘り下げていきます。
日本がIWCを脱退した理由
IWCとは何か
国際捕鯨委員会(IWC)は、1948年に発効した国際捕鯨取締条約に基づいて設立された国際機関です。当初は鯨資源の適切な保存と捕鯨産業の秩序ある発展を目的としていました。しかし、時代とともにその性格は大きく変化していきます。
商業捕鯨モラトリアムの導入
1982年、IWCは商業捕鯨のモラトリアム(一時停止)を決定し、1986年から実施されました。これは鯨資源の減少を受けた措置でしたが、日本はこの決定に異議を唱え続けてきました。
日本政府は、科学的根拠に基づけば、一部の鯨種については持続可能な捕獲が可能であると主張していました。実際、ミンククジラなど一部の種は資源量が回復していると科学委員会も認めていたのです。
日本が脱退を決断した背景
日本がIWC脱退を決断した主な理由は以下の通りです
1. IWCの機能不全
日本は長年にわたり、IWC内で商業捕鯨の部分的再開を提案してきました。しかし、反捕鯨国の増加により、科学的データに基づく議論が困難になっていました。IWCは本来、鯨資源を管理しながら持続可能な利用を図る機関でしたが、実質的に「捕鯨禁止機関」と化していたのです。
2. 調査捕鯨への国際的批判
日本は商業捕鯨モラトリアム後も、科学調査目的の調査捕鯨を南極海などで実施していました。しかし、2014年には国際司法裁判所(ICJ)が日本の南極海での調査捕鯨を条約違反と判断。これにより、日本の調査捕鯨プログラムは大幅な制約を受けることになりました。
3. 持続可能な利用という考え方の相違
日本は、適切に管理された捕鯨は持続可能であり、海洋資源の合理的利用の一形態であると考えていました。一方、反捕鯨国の多くは、鯨を特別な存在と見なし、その捕獲自体に倫理的な問題があるという立場を取っていました。この根本的な価値観の違いが、対話を困難にしていたのです。
4. 日本近海での商業捕鯨再開
IWCを脱退することで、日本は自国の排他的経済水域(EEZ)内で商業捕鯨を再開できるようになりました。これにより、国際的な制約を受けずに、日本の伝統的な捕鯨文化を維持し、沿岸捕鯨地域の経済を支えることが可能になると政府は判断しました。
国内外からの批判
国際社会からの批判
日本のIWC脱退決定は、国際社会から強い批判を受けました。
環境保護団体の反応
グリーンピースやシー・シェパードなどの環境保護団体は、日本の決定を強く非難しました。彼らは、鯨は知能が高く社会性のある生物であり、その捕獲は倫理的に許されないと主張しています。また、海洋生態系における鯨の重要性を指摘し、捕鯨が生態系全体に悪影響を及ぼす可能性を警告しました。
各国政府の反応
オーストラリア、ニュージーランド、欧州諸国など多くの国々が日本の決定に失望を表明しました。これらの国々では、捕鯨は時代遅れで残酷な行為と見なされており、日本の決定は国際協調の精神に反するものだとされました。
一方で、ノルウェーやアイスランドなど、捕鯨を続けている国々もあり、国際社会の見解が必ずしも一枚岩ではないことも事実です。
国内での賛否
日本国内でも意見は分かれました。
賛成派の意見
- 伝統文化の維持:捕鯨は日本の伝統的な食文化の一部である
- 資源の持続可能な利用:科学的根拠に基づいた捕鯨は問題ない
- 食料安全保障:海洋資源の多様な利用は重要
- 地域経済の維持:捕鯨地域の経済と雇用を守る必要がある
反対派の意見
- 動物福祉の観点:鯨は知能が高く、捕獲は残酷
- 国際的な孤立:国際協調を損なう
- 需要の減少:実際の鯨肉需要は限定的で、経済的合理性が低い
- 環境保護:海洋生態系保全の観点から問題がある
漁師の生活と代替案の重要性
この問題を考える上で、私たちが見落としてはならない重要な視点があります。それは、捕鯨に従事してきた漁師やその家族、そして捕鯨で成り立ってきた地域社会の生活です。
捕鯨地域の現実
日本には、和歌山県太地町、千葉県南房総市、宮城県石巻市など、古くから捕鯨と深く結びついてきた地域があります。これらの地域では、捕鯨は単なる産業ではなく、地域のアイデンティティや文化の核となってきました。
捕鯨に従事する人々にとって、それは先祖代々受け継いできた技術であり、生計を立てる手段であり、誇りでもあります。捕鯨船の乗組員、鯨肉加工業者、関連産業に従事する人々など、多くの人々の生活が捕鯨と結びついているのです。
「ただの反対」の限界
私自身、動物福祉や環境保護の観点から捕鯨に対して批判的な気持ちを抱いています。鯨が高度な知能を持ち、複雑な社会構造を持つ生物であることを知れば、その捕獲に心を痛めるのは自然なことでしょう。
しかし、同時に私たちが向き合わなければならないのは、「では、捕鯨に従事している人々の生活はどうするのか」という現実的な問題です。
単純に「捕鯨をやめるべきだ」と主張するだけでは、漁師の人たちの生活を脅かすことになります。彼らに対して、「伝統を捨てろ」「職を変えろ」と一方的に要求することは、倫理的とは言えません。
代替案なき反対は、結局のところ無責任な批判に過ぎません。もし私たちが本当に捕鯨を減らしたい、あるいはなくしたいと考えるなら、同時に以下のような具体的な代替案を提示し、支援する必要があります。
必要な代替案とは
1. 経済的代替手段の提供
捕鯨地域に新たな産業や雇用機会を創出することが不可欠です。例えば:
- ホエールウォッチングなどのエコツーリズム
- 海洋資源を活用した新しい産業(養殖、海洋再生可能エネルギーなど)
- 地域の特産品開発や観光業の振興
- 漁業の他分野への転換支援
2. 移行期間の経済支援
新しい産業への転換には時間とコストがかかります。その移行期間における所得補償や再教育プログラムなどの支援が必要です。
3. 文化的アイデンティティの維持
捕鯨地域の文化や歴史を尊重しながら、新しい形での地域アイデンティティの構築を支援することも重要です。捕鯨博物館や文化施設の整備などが考えられます。
4. 段階的な移行計画
急激な変化は地域社会に大きな混乱をもたらします。長期的な視点に立った段階的な移行計画が必要です。
このような具体的な代替案なしに「捕鯨反対」を叫ぶだけでは、問題は解決しません。むしろ、捕鯨従事者との対立を深めるだけです。
個人でできること
では、一個人として、この複雑な問題に対して私たちは何ができるのでしょうか。
1. 鯨肉を食べないという選択
最も直接的で実行可能なアクションは、鯨肉を食べないことです。
現代の日本において、鯨肉は日常的な食材ではありません。実際、多くの日本人は鯨肉を食べる機会がほとんどないでしょう。スーパーマーケットで鯨肉を見かけることも稀です。
鯨肉を食べないという個人の選択は、需要を減らすことにつながります。需要が減れば、経済的な理由から捕鯨の規模も自然と縮小していく可能性があります。
これは、誰かに迷惑をかけることなく、強制することなく、個人の信念に基づいて実行できる行動です。
2. 情報を集め、理解を深める
この問題について、一方的な情報だけでなく、多様な視点から学ぶことが重要です。
- 捕鯨の歴史と文化的背景を理解する
- 鯨の生態や海洋生態系における役割を学ぶ
- 捕鯨地域の経済的・社会的状況を知る
- 国際的な資源管理の仕組みを理解する
- 動物福祉の観点を学ぶ
複雑な問題だからこそ、単純化せず、多面的に理解する努力が必要です。
3. 建設的な対話に参加する
SNSなどで捕鯨問題が話題になったとき、感情的な非難や一方的な主張ではなく、建設的な対話を心がけることができます。
- 相手の立場や背景を理解しようとする
- 代替案を含めた現実的な議論をする
- 事実に基づいた冷静な意見交換を行う
4. 持続可能な消費を心がける
鯨肉だけでなく、海洋資源全般について持続可能な消費を心がけることも重要です。
- 乱獲されている魚種を避ける
- 海洋環境に配慮した漁法で獲られた水産物を選ぶ
- 認証制度(MSC認証など)を参考にする
- 地域の持続可能な漁業を支援する
5. 教育と啓発
特に次世代に対して、海洋環境や生物多様性の重要性を伝えていくことも大切です。
6. 代替産業への支援
もし可能であれば、捕鯨地域のホエールウォッチングツアーに参加したり、地域の他の特産品を購入したりすることで、代替産業の発展を支援することもできます。
7. 政策への意見表明
選挙での投票や、政治家・政府への意見表明を通じて、海洋政策に影響を与えることも一つの方法です。
私たちが考えるべきこと
バランスの取れた視点の重要性
捕鯨問題は、環境保護、動物福祉、文化の尊重、経済的生存、国際協調など、多くの価値観が交錯する複雑な問題です。どれか一つの視点だけから判断するのではなく、バランスの取れた視点を持つことが重要です。
「正義」の押し付けへの警戒
環境保護や動物福祉は重要な価値ですが、それを絶対視して他者に押し付けることには慎重であるべきです。特に、文化的背景や経済的事情が異なる人々に対して、一方的に自分たちの価値観を強要することは、新たな対立を生むだけです。
真の解決には、対話と理解、そして具体的な支援策が必要なのです。
長期的視点の必要性
この問題は一朝一夕には解決しません。急激な変化は様々な副作用を生みます。長期的な視点に立って、段階的に、そして持続可能な形で変化を促していく必要があります。
私たち自身の消費行動を見つめ直す
鯨肉を食べないという選択をする一方で、私たち自身の日常的な消費行動全体を見つめ直すことも重要です。
乱獲された魚、環境破壊的な農業で生産された食品、過剰なプラスチック使用など、私たちの日常生活には環境や動物に負荷をかけている側面が数多くあります。
捕鯨だけを取り上げて批判するのではなく、自分自身の生活全体を持続可能なものにしていく努力が求められています。
まとめ
日本のIWC脱退は、長年にわたる国際的な対立の一つの帰結でした。科学的データに基づく資源管理という日本の立場と、鯨を特別視する反捕鯨国の立場との間に橋を架けることができなかったのです。
この問題に対して、私たちは簡単に白黒をつけることはできません。環境保護の重要性を認識しながらも、捕鯨に従事してきた人々の生活や文化を無視することはできないからです。
批判するのは簡単です。しかし、代替案なき批判は無責任です。もし私たちが本当に変化を望むなら、具体的な代替策を提示し、支援する必要があります。
同時に、個人としてできることもあります。鯨肉を食べないこと、情報を集めて理解を深めること、建設的な対話に参加すること、持続可能な消費を心がけること。これらは小さな行動かもしれませんが、一人ひとりの選択が積み重なることで、社会は変わっていきます。
大切なのは、一方的な価値観の押し付けではなく、多様な立場を理解し、対話を通じて、すべての人々にとってより良い解決策を見つけていくことです。
捕鯨問題は、私たちに人間と自然の関係、文化と倫理、経済と環境のバランスについて深く考える機会を与えてくれます。簡単な答えはありませんが、それでも私たちは考え続け、行動し続けなければなりません。
一人ひとりができることから始める。それが、この複雑な問題に対する現実的で、誠実なアプローチなのではないでしょうか。
古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。
参加しやすいものにぜひ協力してください!
関連情報