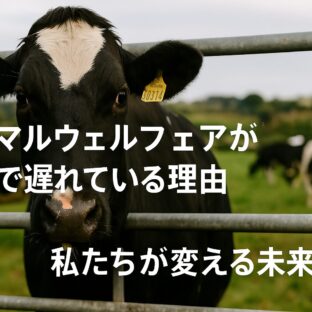世界動物保護協会とは – 日本の畜産業界に求められる変革
世界動物保護協会(WAP)の概要
世界動物保護協会(World Animal Protection、略称WAP)は、1981年に設立された国際的な動物保護団体です。本部をイギリス・ロンドンに置き、世界50カ国以上で活動を展開している世界有数の動物福祉団体として知られています。
この組織は、家畜動物、野生動物、災害時の動物、そしてペットなど、あらゆる動物の福祉向上を目指して活動しています。特に畜産動物の飼育環境改善、野生動物の保護、動物実験の削減など、幅広い分野で政策提言や啓発活動を行っています。
世界動物保護協会の最大の特徴は、企業や政府と協力しながら、実効性のある変革を推進していく点にあります。批判だけでなく、建設的な対話を通じて、持続可能で倫理的な解決策を模索する姿勢が評価されています。
日本でも少しずつ知られてきたAPIと動物福祉の評価
近年、日本国内でも「API(Animal Protection Index:動物保護指数)」という指標が注目を集めるようになってきました。これは世界動物保護協会が開発した、各国の動物保護政策を評価するための国際的な指標です。
APIは、各国の動物福祉に関する法律、政策、実施状況などを総合的に評価し、AからGまでのランクで格付けします。この評価には、畜産動物の飼育環境、野生動物保護、動物実験規制、ペット保護など、複数の観点が含まれています。
残念ながら、日本のAPI評価は決して高くありません。特に畜産動物の福祉に関する項目では、先進国の中でも低い評価を受けているのが現状です。これは日本の畜産業界において、動物福祉への配慮が十分でないことを示しています。
具体的には、日本では畜産動物の飼育に関する具体的な基準が法律で定められていないケースが多く、過密飼育や身動きが取れないような環境での飼育が一般的に行われています。例えば、採卵鶏のバタリーケージ飼育、妊娠豚のストール飼育など、多くの先進国で禁止または制限されている飼育方法が、日本では今もなお主流となっています。
日本動物福祉協会や日本SPCAなどの国内団体も、世界動物保護協会と連携しながら、こうした状況の改善を訴えています。しかし、畜産業界の経済的な懸念や、消費者の価格志向などから、変革は容易には進んでいません。
それでも、近年はメディアでも動物福祉の問題が取り上げられるようになり、一般消費者の間でも関心が高まりつつあります。特に若い世代を中心に、エシカル消費やアニマルウェルフェアに配慮した商品を選ぶ動きが広がっています。
世界から見た日本の畜産 – 東京オリンピックが示した課題
2020年(実際には2021年開催)の東京オリンピック・パラリンピックは、日本の畜産業界にとって一つの転換点となりました。オリンピックの開催に伴い、世界中から日本の動物福祉水準に対する批判が集まったのです。
国際オリンピック委員会(IOC)は、持続可能性を重視する方針を掲げており、大会で提供される食材についても動物福祉基準を満たすことを推奨していました。しかし、日本国内でこれらの基準を満たす畜産物を十分に調達することが困難であることが明らかになりました。
海外の動物保護団体からは、日本の畜産業界における過密飼育、狭いケージでの飼育、適切な飼育環境の欠如などが指摘されました。特にEU諸国やオーストラリアなど、動物福祉基準が確立している国々からの視線は厳しいものでした。
この出来事をきっかけに、日本国内でも「このままの畜産環境ではいけない」という意識が広まりつつあります。大手食品企業やレストランチェーンの中には、動物福祉に配慮した調達方針を発表するところも出てきました。
また、消費者の間でも、「安ければいい」という考え方から、「動物にとっても、環境にとっても、人間にとっても良い選択をしたい」という価値観へのシフトが起こり始めています。
他の国と日本を比べる必要性と独自性のバランス
「他の国と日本とを比べる必要もないし、日本は日本のやり方の畜産で良い」という意見も確かに存在します。日本には日本の気候、文化、経済状況があり、欧米のやり方をそのまま導入することが必ずしも最適とは限りません。
しかし、動物福祉という観点は、文化的相対性を超えた普遍的な倫理の問題でもあります。動物が痛みを感じる能力を持つ生き物であることは科学的事実であり、不必要な苦痛を与えないという原則は、どの国においても尊重されるべきものです。
日本の伝統的な畜産業には、実は動物との共生を重視する要素もありました。小規模な家族経営の農場では、動物一頭一頭に名前をつけ、大切に育てる文化がありました。しかし、経済成長と効率化の追求の中で、そうした伝統的な価値観は失われ、工業的な大量生産システムが主流となってしまったのです。
今求められているのは、単に欧米の基準を模倣することではなく、日本の気候風土や文化的背景を踏まえつつ、科学的根拠に基づいた動物福祉基準を確立することです。実際、アジア諸国の中でも、韓国や台湾では動物福祉法の整備が進んでおり、日本が参考にできる事例は増えています。
グローバル化が進む現代において、国際的な倫理基準から大きく外れることは、長期的には日本の畜産業や食品産業にとってもリスクとなります。既にEUなどでは、動物福祉基準を満たさない国からの輸入を制限する動きも出始めています。
時代とともに変わる価値観 – 動物に対する意識の転換期
世の中は時代によって価値観が変わります。かつて当たり前だったことが、今では受け入れられないということは歴史上何度も繰り返されてきました。
今、私たちは動物に対する意識が大きく変わろうとしている潮目にいます。科学の発展により、動物の認知能力や感情についての理解が深まり、動物を単なる「モノ」や「資源」としてではなく、感覚を持つ存在として認識する動きが世界的に広がっています。
特に若い世代の間では、環境問題、気候変動、そして動物福祉が密接に関連していることが認識されています。工業的畜産は温室効果ガスの主要な排出源の一つであり、動物福祉への配慮は環境保護とも両立する取り組みなのです。
また、ペットを家族の一員として大切にする文化が日本でも定着する中で、「なぜ犬や猫は大切にされるのに、豚や鶏は過酷な環境で飼育されるのか」という疑問を持つ人も増えています。この「種による差別」についての議論も、動物福祉を考える上で重要な視点となっています。
SNSの普及により、これまで見えなかった畜産の現場の実態が可視化されるようになったことも、意識変革を後押ししています。工場式畜産の実態を知った多くの人々が、ショックを受け、何かを変えたいと思うようになっているのです。
環境の「当たり前」の異常性に気づく
私たちは、自分が置かれている環境に慣れてしまうと、それが当たり前になってしまい、その異常さに気が付きにくくなります。これは心理学で「正常性バイアス」とも呼ばれる現象です。
日本の畜産業界で働く人々の多くは、決して動物を虐待しようと思っているわけではありません。しかし、業界の常識や経済的な制約の中で、結果的に動物に大きな苦痛を与える飼育方法が「普通のこと」として受け入れられてしまっているのです。
例えば、採卵鶏がA4サイズにも満たないケージの中で一生を過ごすこと。妊娠豚が体を転回することもできない狭いストールに閉じ込められること。肉用鶏が過度の品種改良により、自分の体重を支えきれずに歩行困難になること。これらはすべて、日本の畜産業界では「標準的な」飼育方法です。
しかし、世界から見たら日本の畜産の仕方は異常であるということを受け止める必要があります。これは日本の畜産業を非難するためではなく、より良い方向に変えていくための第一歩なのです。
EU諸国の多くでは、バタリーケージの使用が禁止され、鶏は止まり木や砂浴び場のある環境で飼育されています。スイスでは、すべての畜産動物に対して詳細な飼育基準が法律で定められています。ニュージーランドでは、動物は「感覚を持つ存在」であることが法律で明記されています。
こうした国際的な動きを知ることで、私たちは自国の現状を客観的に見つめ直すことができます。そして、「このままでいいのだろうか」という問いを自分自身に投げかけることができるのです。
変えたいと思う人が行動すれば必ず変えられる
現状は確かに厳しいものです。しかし、希望もあります。歴史を振り返れば、多くの社会変革は、少数の「変えたい」と強く思う人々の行動から始まっています。
動物福祉の分野でも、世界各国で大きな変化が起きてきました。かつては工場式畜産が主流だった欧米諸国でも、市民や NGO の粘り強い活動により、法律が改正され、企業の方針が変わり、消費者の選択肢が広がってきました。
日本でも、変化は始まっています。一部の生産者は、平飼いや放牧といった動物福祉に配慮した飼育方法に転換しています。大手スーパーの中には、アニマルウェルフェア認証を受けた商品の取り扱いを増やしているところもあります。
企業に対して、消費者として声を上げることも重要です。「動物福祉に配慮した商品を求めています」というメッセージを企業に伝えることで、企業の方針を変える力になります。実際、海外では消費者の声を受けて、大手食品企業が次々とケージフリー宣言を行っています。
政治家や行政に対して、法整備を求める声を届けることも効果的です。署名活動に参加したり、議員に手紙を書いたり、パブリックコメントで意見を表明したりすることで、政策を動かすことができます。
そして何より、自分自身の消費行動を変えることが最も直接的な行動です。動物福祉に配慮した商品を選ぶ、肉の消費量を減らす、植物性の代替食品を試してみるなど、日々の選択が積み重なって大きな変化を生み出します。
世界動物保護協会の具体的な活動
世界動物保護協会は、具体的にどのような活動を行っているのでしょうか。その取り組みを知ることで、私たちも何ができるかのヒントが得られます。
企業との対話と協働 世界動物保護協会は、食品企業やレストランチェーンと対話し、動物福祉基準の導入を促しています。批判するだけでなく、実現可能な改善策を提案し、企業の取り組みをサポートする姿勢が特徴です。
政策提言活動 各国政府に対して、科学的根拠に基づいた動物福祉法の制定や改正を働きかけています。専門家と連携し、実効性のある政策案を提示することで、法整備を推進しています。
消費者教育と啓発 一般市民に対して、畜産の実態や動物福祉の重要性について情報提供を行っています。ウェブサイト、SNS、イベントなどを通じて、分かりやすく情報を発信しています。
生産者支援 動物福祉に配慮した飼育方法に転換しようとする生産者を支援するプログラムも実施しています。技術的なアドバイスや、成功事例の共有などを通じて、実践的なサポートを提供しています。
国際的なネットワーク構築 世界各国の動物保護団体、研究機関、政府機関などと連携し、グローバルな動きを作り出しています。国際会議の開催や、共同キャンペーンの実施などを通じて、世界的な意識向上を図っています。
日本における今後の展望
日本の畜産業界が変わるためには、複数のステークホルダーの協力が必要です。
生産者の役割 経済的な制約がある中でも、段階的に飼育環境を改善していく努力が求められます。先進的な取り組みを行っている生産者の事例を学び、実現可能な改善から始めることが重要です。
企業の役割 食品企業や小売業は、調達方針を見直し、動物福祉に配慮した商品の取り扱いを増やすことができます。また、サプライチェーン全体での改善を推進するリーダーシップも期待されます。
政府の役割 具体的で実効性のある動物福祉基準を法律で定めることが急務です。同時に、基準を満たすための支援策や移行期間の設定など、生産者が対応できる環境を整備することも必要です。
消費者の役割 私たち消費者は、購買行動を通じて市場を変える力を持っています。価格だけでなく、動物福祉や環境への配慮も含めた総合的な価値で商品を選ぶことが、持続可能な社会への貢献となります。
研究機関の役割 日本の気候風土や飼育環境に適した、科学的根拠に基づく動物福祉基準の研究開発が求められます。また、改善による経済的影響の評価なども重要な研究テーマです。
まとめ – 一人ひとりができることから始めよう
世界動物保護協会とは、動物の苦痛を減らし、福祉を向上させるために世界規模で活動する国際組織です。その活動を通じて、私たちは日本の畜産業界が抱える課題を客観的に認識することができます。
東京オリンピックをきっかけに、日本の畜産に対する世界からの視線が厳しくなったことは事実です。しかし、これは日本を批判するためではなく、より良い方向に変わるための機会でもあります。
確かに、「日本は日本のやり方で良い」という考え方もあるでしょう。しかし、動物福祉という普遍的な倫理的課題に対して、私たちは目を背けることはできません。世界から見て異常と思われる現状を、まずは正直に受け止めることが重要です。
そして、その環境に慣れてしまい、異常さに気が付きにくくなっている私たちだからこそ、外部からの指摘に耳を傾け、学ぶ姿勢が必要なのです。
幸いなことに、変えたいと思う人が行動をしていけば、社会は必ず変えられます。歴史がそれを証明していますし、現在進行形で世界各国で変化が起きています。
一人ひとりができることは小さいかもしれません。しかし、知ること、考えること、選択を変えること、声を上げること。そうした小さな行動の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出します。
世界動物保護協会のような国際組織の活動を知り、その視点を学ぶことは、私たち自身の意識を変える第一歩です。そして、日本の畜産業界が、動物にとっても、環境にとっても、そして生産者や消費者にとっても持続可能な形に変わっていくことを、私たち一人ひとりが支えていくことができるのです。
今、私たちは大きな価値観の転換期にいます。動物をどう扱うべきかという問いは、私たちの社会がどのような未来を選ぶのかという問いでもあります。より思いやりのある、倫理的な社会を次世代に残すために、今できることから始めてみませんか。
古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。
参加しやすいものにぜひ協力してください!
関連情報