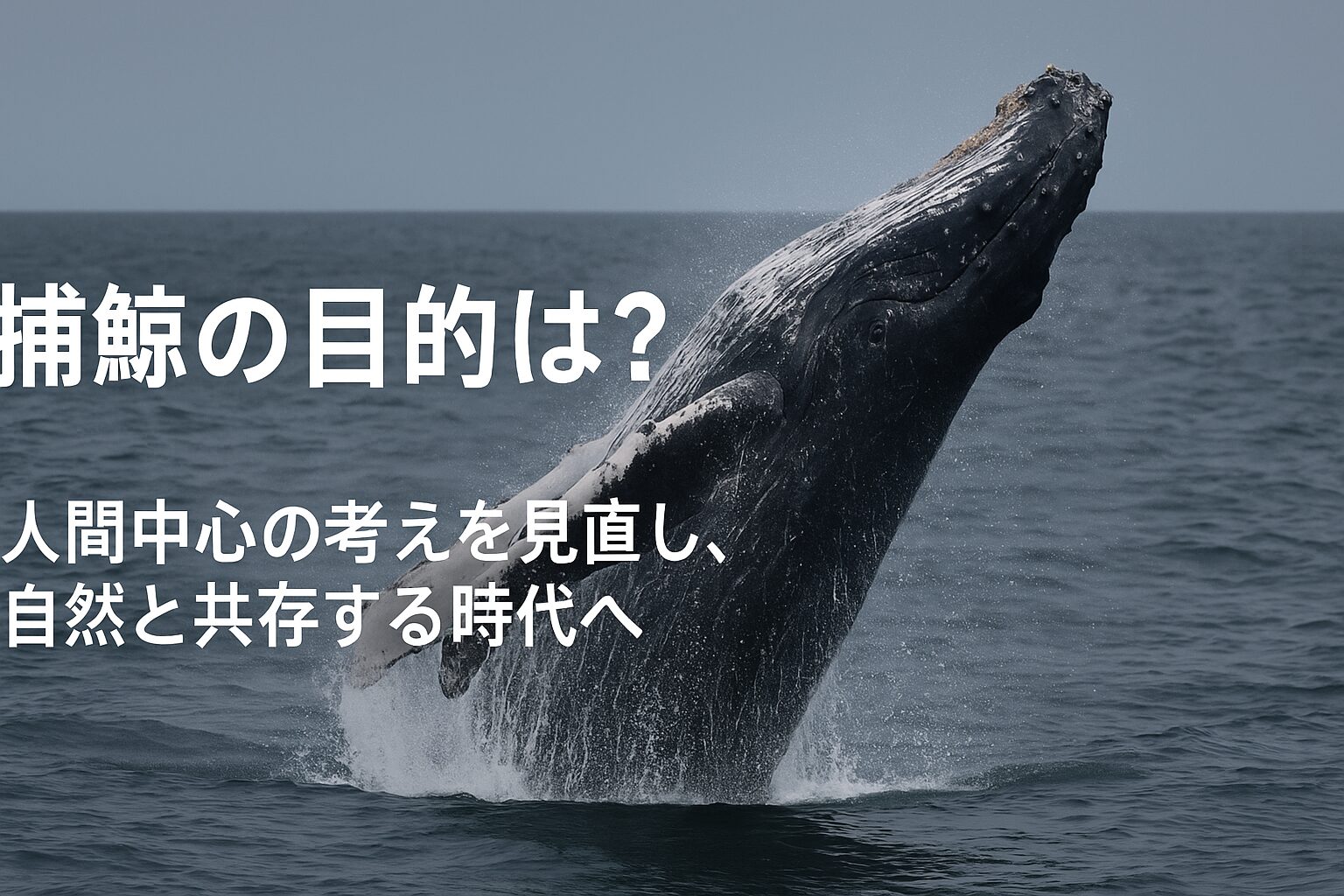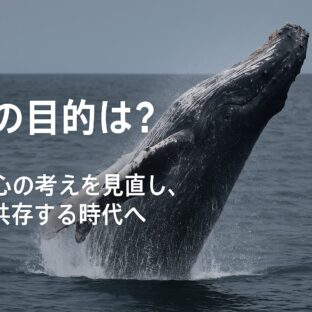捕鯨の目的を問い直す:人間中心主義からの脱却
はじめに
「捕鯨 目的」と検索する人々は、なぜ日本が今もクジラを捕り続けるのか、その理由を知りたいと思っているのでしょう。本記事では、日本における捕鯨の目的を検証しながら、その根底にある人間中心主義的な価値観に疑問を投げかけます。私は捕鯨反対の立場から、これからの時代に必要な新しい価値観について考えていきたいと思います。
日本が捕鯨を続ける目的とは
1. 食文化の継承という主張
日本政府や捕鯨関係者がもっとも強調するのが「伝統的な食文化の保護」という目的です。確かに、日本の沿岸部では古くからクジラを食してきた歴史があります。江戸時代には組織的な捕鯨が行われ、クジラ肉は庶民の食卓にも上る身近な食材でした。
しかし、ここで立ち止まって考えるべきことがあります。文化とは、固定された不変のものではありません。時代の価値観によって、残されるものと消えていくものがあります。かつて日本には多くの伝統がありましたが、現代の倫理観や社会状況に合わないものは自然と姿を消していきました。
個体数が減少している生物を食べ続けることを「文化」という言葉で正当化できるのでしょうか。
クジラの種類によっては絶滅が懸念されるほど個体数が減少しています。そのような状況下で、あえて捕獲を続ける必要性があるのか、真剣に問い直す時期に来ているのではないでしょうか。
2. 科学的調査という名目
長年、日本は「調査捕鯨」という名目で捕鯨を続けてきました。これは国際捕鯨取締条約で認められた特別許可に基づくものでした。しかし、2019年に日本は国際捕鯨委員会(IWC)から脱退し、商業捕鯨を再開しています。
調査という名目であっても、捕獲されたクジラの肉は市場に流通していました。これに対して国際社会からは「調査を隠れ蓑にした商業捕鯨だ」という批判が絶えませんでした。本当に科学的データが必要なら、致死的でない調査方法も存在します。現代の技術を使えば、クジラを殺さずに多くの情報を得ることが可能なのです。
3. 海洋資源管理という理由
捕鯨推進派がよく持ち出す論理に「クジラが大量の魚を食べるから、人間の漁獲量が減る」というものがあります。つまり、クジラを間引くことで漁業資源を守るという主張です。
しかし、この考え方こそが人間の傲慢さの象徴ではないでしょうか。
「クジラが魚を食べる」論の問題点
人間はいつからそんなに偉くなったのか
「クジラが魚を食べるから人間の取り分が減る」という発想には、重大な前提が隠されています。それは「海の資源は人間のものである」という考えです。
海洋生態系は何百万年もかけて形成されてきた複雑なバランスの上に成り立っています。クジラはその生態系の重要な一部であり、長い進化の歴史の中で今の個体数と捕食行動を獲得してきました。人間が漁業を始めるはるか以前から、クジラは海で魚を食べてきたのです。
それなのに、人間が「クジラのせいで魚が減る」と主張するのは、あまりにも身勝手ではないでしょうか。
実際には、世界的な魚類資源の減少の主な原因は、人間による過剰漁獲、海洋汚染、気候変動などです。クジラを捕獲したところで、これらの根本的な問題は何も解決しません。むしろ、クジラという便利なスケープゴートを作り出すことで、人間自身の責任から目を逸らしているとも言えます。
生態系における役割
近年の研究では、クジラが海洋生態系において重要な役割を果たしていることが明らかになっています。クジラの排泄物は海の表層に栄養を供給し、植物プランクトンの成長を促します。この植物プランクトンは食物連鎖の基盤であると同時に、大量の二酸化炭素を吸収する存在でもあります。
つまり、クジラを保護することは、魚類資源の維持だけでなく、地球全体の気候変動対策にもつながる可能性があるのです。これは「クジラvs人間」という対立構造で語られるべき問題ではなく、共生の視点から考えるべき課題なのです。
「食文化」という言葉の陰で
本当に必要な食材なのか
捕鯨推進派は「クジラ肉は日本の伝統的な食文化」だと主張します。しかし、現代の日本において、クジラ肉がどれほど日常的に消費されているでしょうか。
統計を見れば明らかですが、クジラ肉の消費量は年々減少しています。スーパーマーケットでクジラ肉を見かけることは稀ですし、日常的に食べている人はごく少数です。学校給食で提供される地域もありますが、それも限定的です。
私たちには他に食べるものが豊富にあります。
牛肉、豚肉、鶏肉、魚類、大豆製品など、タンパク源は多様に存在します。わざわざ個体数が減少している生物を捕獲して食べる必然性は、栄養学的にも経済的にも見出せません。
文化は時代とともに変わる
文化の継承は大切です。しかし、すべての伝統を無批判に守り続けることが正しいわけではありません。
かつて日本には仇討ちの文化がありました。武士道の一部として称賛されていた時代もありました。しかし、現代社会の法治主義や人権意識の発展とともに、この文化は歴史の中に位置づけられました。
同様に、動物の権利や生物多様性への意識が高まる現代において、捕鯨という文化をどう位置づけるかは、私たちが選択すべき問題です。「昔からやっているから」という理由だけで継続することは、思考停止に他なりません。
文化が残るかどうかは、その時代の価値観によって決まります。
そして今、私たちの価値観は大きな転換点を迎えているのです。
価値観の変遷:生産・消費から共生へ
高度経済成長期の価値観
振り返ってみれば、日本は戦後の復興から高度経済成長を遂げる過程で、ある種の価値観を強固に内面化してきました。それは「生産すること」「消費すること」「経済を回すこと」を最優先する考え方です。
自然は「資源」として、つまり人間が利用するための材料として位置づけられました。森林は木材として、海は漁場として、山は鉱物の採掘場として。自然界の生物たちは、経済活動の対象か、あるいは邪魔者として扱われてきたのです。
この時代、捕鯨は「海洋資源の有効活用」として正当化されました。クジラは食料であり、油は工業製品の原料でした。経済発展のためには、自然から可能な限り多くを搾取することが美徳とされたのです。
失われた自然との調和
しかし、かつての日本人は本当にそうだったのでしょうか。
江戸時代やそれ以前の日本では、人々は自然との調和を重視していました。山の神、海の神への畏敬の念があり、自然から恵みをいただくことへの感謝が日常に溢れていました。必要以上に採らない、来年もまた恵みを得られるように節度を守る、そういった知恵が生活の中に息づいていました。
いつの間に私たちはこの感覚を失ってしまったのでしょうか。
近代化と経済成長の波の中で、自然への畏敬は「非科学的」「時代遅れ」とされました。効率と生産性が全てを支配する社会になりました。そして気づいた時には、森林は減少し、海は汚染され、多くの生物が絶滅の危機に瀕していました。
次世代への責任
今、私たちは大きな岐路に立っています。
このまま人間中心主義的な価値観を続けるのか、それとも自然との共生を目指す新しい価値観へと転換するのか。この選択は、私たちの世代だけでなく、未来の世代の生活環境をも決定づけます。
次の世代の価値観は、人間中心ではなく、自然のことも配慮する時代へと移行すべきです。
気候変動、生物多様性の喪失、海洋プラスチック問題など、人類は今、自らの活動が引き起こした環境危機に直面しています。これらの問題を解決するには、根本的な価値観の転換が必要です。人間だけが地球の主人公ではなく、すべての生命が共存する惑星の一員であるという認識を持つこと。これが次世代に求められる視点なのです。
捕鯨問題から見える日本の課題
国際社会との乖離
日本が商業捕鯨を再開したことは、国際社会から厳しい批判を受けました。多くの先進国が捕鯨を非人道的と見なし、クジラを保護すべき対象と考える中、日本の姿勢は孤立を深めています。
これは単に捕鯨の是非だけの問題ではありません。環境問題や動物の権利に対する国際的な潮流に、日本がどう向き合うのかという、より大きな問題を象徴しています。
「他国に口出しされる筋合いはない」という反発も理解できます。しかし、海は世界中の人々が共有する資源であり、クジラは回遊する生物です。一国の判断だけで済む問題ではないのです。
経済合理性の欠如
実は、現代の捕鯨は経済的にも疑問符がつきます。
捕鯨船の運航には多額の費用がかかります。クジラ肉の需要が低下する中、これらの費用を市場価格だけで回収することは困難です。実際、捕鯨産業は政府からの補助金に依存している側面があります。
つまり、税金を投入してまで、需要の少ないクジラ肉を供給し続けているのが現状なのです。この資金を他の持続可能な漁業の発展や、海洋環境の保護に使った方が、長期的には日本の海洋産業にとってプラスになるのではないでしょうか。
世代間の意識の差
興味深いことに、捕鯨に対する賛否は世代によって大きく異なります。
高齢世代には実際にクジラ肉を食べた記憶があり、捕鯨を支持する傾向が強くあります。一方、若い世代は環境教育を受けて育ち、動物の権利や生物多様性への意識が高く、捕鯨に否定的な人が多いのです。
この世代間ギャップは、価値観が確実に変化していることの証拠です。時間とともに、社会全体の合意も変わっていく可能性があります。
世界が捕鯨をやめた理由
多くの国々は、クジラの個体数減少を理由に商業捕鯨を禁止しています。
アメリカやイギリス、オーストラリアなどでは、クジラは「観光資源」として守られる存在となっています。
クジラウォッチングによって地域経済を潤す事例も多く、「捕る」よりも「見る」ことで共存する社会がすでに実現しています。
世界が捕鯨をやめたのは、単に「反対運動が強かったから」ではなく、命を奪う文化から、共に生きる文化へと価値観が変化したからです。
捕鯨を続ける日本の課題
日本が捕鯨を続ける背景には、政治的・経済的な事情もあります。
一部の地域では捕鯨が雇用を支え、関連産業があるのも事実です。
しかし、政府が「伝統文化」や「地域振興」を理由に補助金を出してまで続けるほどの産業なのでしょうか。
実際、クジラ肉の消費量は年々減少し、若い世代で食べたことがある人はごくわずかです。
つまり、需要がないのに供給を続けている構造なのです。
この構図は「文化を守る」ではなく、「既得権益を守る」行為に近いと感じます。
私が捕鯨に反対する理由
私は、クジラを食べることが「悪」だと言いたいのではありません。
ただ、現代の社会においてそれを続ける理由がないと思っています。
人間は自然の一部であり、他の生き物と共に生きていく存在です。
それなのに、「魚を食べすぎるから」「伝統だから」という理由で命を奪うことは、人間中心の価値観そのものです。
クジラが海で生きる姿を想像すれば、その命の尊さを感じられるはずです。
私たちは、命を奪わなくても豊かに生きられる時代に生きています。
だからこそ、食べなくてもいい命は奪わないという選択が求められています。
代替案:クジラとの新しい関係
ホエールウォッチングの可能性
クジラを殺さずに経済的価値を生み出す方法があります。それがホエールウォッチングです。
世界中で、ホエールウォッチングは大きな観光産業になっています。生きているクジラを見るために、多くの観光客が訪れ、地域経済を潤しています。ある試算によれば、1頭のクジラが生涯にわたってホエールウォッチングで生み出す経済効果は、肉として売った場合の何倍にもなるそうです。
日本の沿岸部でも、ホエールウォッチングを展開している地域があります。これを拡大することで、捕鯨に代わる持続可能な海洋産業を育てることができます。
教育と研究の拠点として
クジラは非常に知的な生物です。その生態、社会構造、コミュニケーション方法など、まだ解明されていないことが数多くあります。
捕鯨ではなく、非致死的な方法での研究を進めることで、日本は海洋生物学の先進国となることができます。研究施設や教育プログラムを整備し、次世代の海洋科学者を育成する。そういった方向性も考えられるのです。
私たちにできること
消費者としての選択
私たち一人ひとりの選択が、社会を変える力を持っています。
クジラ肉を買わない、食べない。これは誰にでもできる意思表示です。需要がなければ、供給も自然と減少していきます。
同時に、持続可能な漁業で獲れた魚を選ぶ、海洋環境に配慮した製品を購入するなど、日常の買い物を通じて海を守ることができます。
声を上げる
民主主義社会では、市民の声が政策を動かします。
捕鯨政策に疑問を感じるなら、それを表明することが大切です。SNSでの発信、自治体への意見、選挙での投票行動など、様々な形で意思を示すことができます。
特に若い世代の声は重要です。これからの社会を作っていく世代が、どんな未来を望むのか。その意志を明確に示すことが、社会変革の原動力になります。
次世代への教育
子どもたちに、自然との共生の大切さを伝えていくことも重要です。
クジラだけでなく、すべての生物に命があり、それぞれが生態系の中で役割を持っていること。人間は自然の一部であり、自然なしには生きていけないこと。こうした基本的な認識を、次の世代に引き継いでいく必要があります。
結論:人間中心主義を超えて
「捕鯨の目的」を問うこの記事の冒頭に戻りましょう。
日本が捕鯨を続ける目的として挙げられるのは、食文化の継承、科学調査、海洋資源管理などです。しかし、これらの理由を詳しく検証すると、いずれも現代社会の文脈では説得力に欠けることが分かります。
根本的な問題は、これらの理由が全て人間中心主義に基づいているということです。
「人間が食べたいから」「人間の漁獲量を増やしたいから」「人間の文化だから」──すべての論理が、人間の都合を最優先しています。クジラという生物の立場、海洋生態系全体のバランス、未来世代が享受すべき自然環境、こういった視点が欠落しているのです。
21世紀を生きる私たちは、20世紀型の価値観から脱却する必要があります。無限の経済成長、自然資源の無制限な利用、人間の欲望を最優先する社会システム。これらはもはや持続可能ではありません。
これからの時代に必要なのは、自然との調和、他の生命への敬意、持続可能性への配慮です。
捕鯨問題は、その象徴的な試金石と言えるでしょう。私たちがこの問題にどう向き合うかは、次の世代にどんな地球を残すのかという、より大きな問いに直結しています。
個体数が減少している生物をわざわざ捕獲して食べる必要はありません。他に食べるものは豊富にあります。クジラは海で自由に泳ぎ、生態系の一部として存在する方が、地球全体にとって有益なのです。
文化は固定されたものではなく、時代とともに進化します。かつて人類は自然を大切にしてきました。近代化の過程でその感覚を失いましたが、今こそ取り戻す時です。人間だけが地球の主役ではない。すべての生命が共存する惑星の一員として、謙虚さを持って生きていく。
そんな価値観を、次の世代に引き継いでいくこと。それが今を生きる私たちの責任ではないでしょうか。
古着買取、ヴィーガン食品やペットフードの買い物で支援など皆様にしてもらいたいことをまとめています。
参加しやすいものにぜひ協力してください!
関連情報